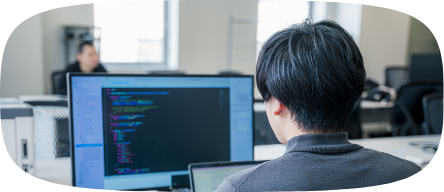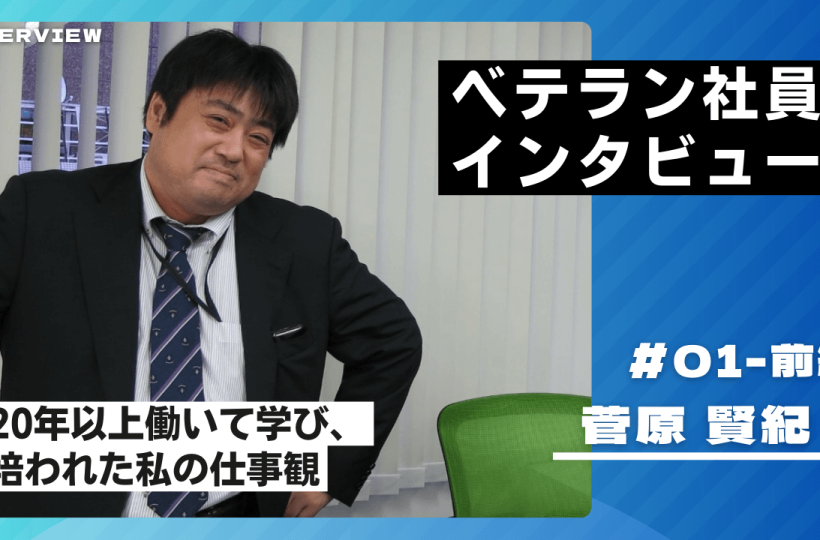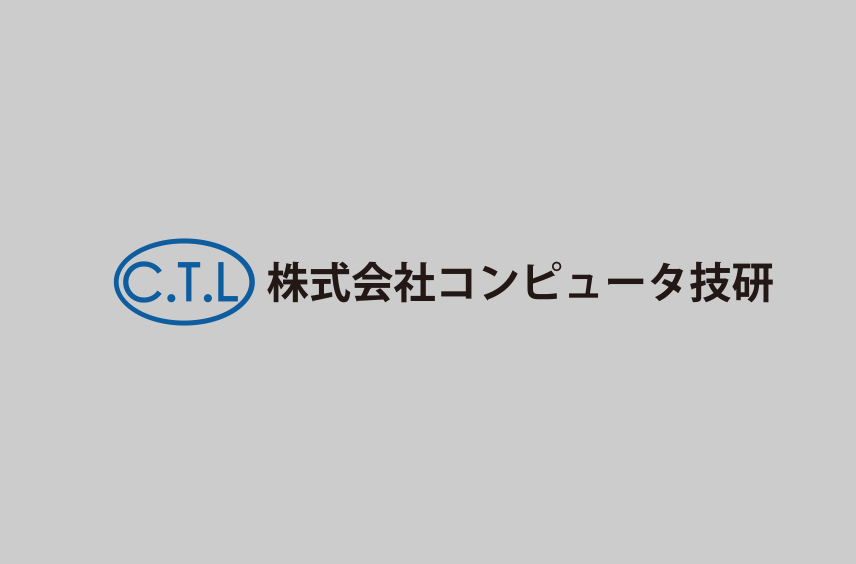プロジェクトを越えて工夫と想いを共有する。リーダー同士で高め合う場のはじまり【PLディスカッション】
社内での取り組み
 Diamond
Diamond
こんにちは、入社5年目の岩藤です。
株式会社コンピュータ技研(以降はC.T.Lと表記)は8つのグループ(部署)を持ち、多くのプロジェクトに取り組んでいます。
そして各プロジェクトには“リーダー”としてチームを牽引する社員がおり、日々さまざまな状況や課題に向き合いながら、それぞれの現場で工夫と想いを持ってチームを導いています。
ただ、現状では「他のリーダーがどんなことを考えて、どんな工夫をしているのか」を広く知る場というものはありませんでした。
結果として、素晴らしい実践が現場内にとどまってしまうことも少なくありません。
そこで、プロジェクトリーダー(以降はPLと表記)が集まる『PLディスカッション』を企画・開催しました。
今回は第1回のディスカッションの様子をご紹介します。
<PLディスカッションとは?>
PLディスカッションとは、
− PL同士が「チームを良くするために取り組む工夫、そして想い」を共有し合う場 −
として、今年度から新たにスタートした取り組みです。
この場では、案件の進捗やスケジュールの話ではなく、
「リーダーとしてどんなことを意識しているか」
「チームづくりでどんな取り組みをしているか」
といった、“人とチーム”に向き合う視点を中心に語り合っています。

<第1回PLディスカッションで語られたこと>
先日、私が所属するグループ内でディスカッションを実施しました。テーマは
【メンバーとのコミュニケーションで意識していること】
各現場での工夫やスタンスが共有されるなかで、「環境をどう作るか」、「どうすれば信頼が生まれるか」という観点が特に多く語られました。
ディスカッションの内容を、見えてきた共通点や特徴ごとに5つの視点に整理してご紹介します。
1. 日常的な会話の仕組みづくり
「会話は自然に生まれるものではなく、意図的に仕掛けていくもの」という共通認識が多くのリーダーに見られました。
- 毎日話すことを意識し、ちょっとした雑談もする
- リモート環境下でも、朝会・夕会を設けて会話の定例イベント化
- 雑談OKのチャットルームを作る
- リモート環境で作業に悩んでいそうな相手に通話をかける、といった一歩進んだ接点を大事にする
リモート・対面に関わらず日常的に「話す時間」を意図して作ることで、相談のハードルを下げることに繋がっているようです。
2. 声をかけやすい空気づくり
「話しかけられる人」になるために、普段からの関係性づくりを大切にしている声も多数ありました。
- 怒らない/責めない/相談は断らない、という姿勢で、“聞いてもらえる存在”になることを意識
- たとえば「今どこ住んでる?」よりも「出身どこ?」のような、適度な距離感から会話を始める
- 朝会の場で、業務以外の会話も取り上げる
- 雑談チャットや軽いトピックを通じて、心理的なハードルを下げておくことが相談のしやすさにつながるという声も。
このような“仕込み”があるからこそ、困ったときに助けを求めやすくなるといった実感がメンバーからも多く共有されました。

3. 相手を尊重する・受け止める姿勢
「聞くこと」の質にも工夫が見られました。
単なる応答ではなく、“身体ごと聞く”ような真剣な姿勢を意識しているリーダーが多くいました。
- 作業の手を止めて、身体を相手に向け目を見て話を聞くことで、「ちゃんと聞いてくれている」と感じてもらえる
- リーダーであっても同じ目線で学ぶ姿勢を見せることで、対話が上下ではなく“並走”になる
- 様子を見ながら声をかけるなど、タイミングや温度感に配慮
「受け入れてもらえる」と感じられる関係性が、相談や挑戦を後押しする土台になっているようです。
4. 個別性を尊重した関わり方
一人ひとりの志向や目標に合わせた接し方も、一部のリーダーが意識していました。
- キャリアビジョンを聞いたうえで、成長に繋がるフィードバックや機会提供を意識
- 明確に「任せる領域」を伝えることで、その領域のキーマンとして自信を育てる
- メンバー一人ずつと毎月会話する時間を設け、雑談をしたり仕事の相談を受ける
これは、「その人自身と、その人の成長」への関心が信頼関係を生むことを意図していると感じました。
5. リーダーとしてのあり方
「技術や知識」だけでなく、「人としてどう関わるか」という“あり方”に触れる場面もありました。
- お客様や他会社の方に紹介し、“橋渡し”役になることで、現場での心理的安全性・繋がりを広げる
- 自分のファンになってもらうことを意識して、「このリーダーのために頑張ろう」と思える関係性を築く
- 「環境づくり」は単なる管理の手段ではなく、チームが自律して機能するための前提と捉える
プロジェクトの種類や立場に関係なく、リーダーが“関係性の起点になる存在”としてチームに向き合っている様子が印象的でした。

<なぜ今、この取り組みを進めたいのか>
C.T.Lが目指す”自律分散型組織”の実現には、ポジションにかかわらず主体性を持って関われる人が増えることが必要だと、私自身は捉えています。
また、C.T.Lに入社する若手の中には、将来的にリーダーを目指したいと考える方も多くいます。
そのためディスカッションは”誰でも聴きに来られるオープンな場所”で開催し、若手も自由に見学できる形で開催していきます。
若手の社員にも、リーダーの姿勢やチームづくりのヒントを間近で感じ、将来の選択肢や自分らしい関わり方を考えるきっかけにしてもらえたらと思っています。

<次回に向けて>
この活動は「答えを出す場」ではありません。
むしろ正解のない問いと向き合いながら、“リーダー同士が高め合える関係性をつくる場”にしたいと思っています。
この場は今後も開催の輪を広げ、定期的に続けていきます。
社員に向けてお伝えすると、「自分の考えをシェアしたい」「他の現場のリーダーの工夫を聞いてみたい」など、関心のある方はぜひ気軽にご参加ください。
また、若手のみなさんの見学も大歓迎です。
リーダーというポジションに限らず、「チームを良くしたい」と思うすべての人にとって、ヒントがある場になるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後もPLディスカッションの内容を発信していきますので、第2回の記事もぜひご覧ください。
 Diamond
Diamond
若手がやりたいと言ったことをやらせてもらえる、そんな会社です。
仕事はもちろん、部活動や社員インタビューもやってます。